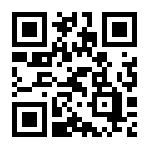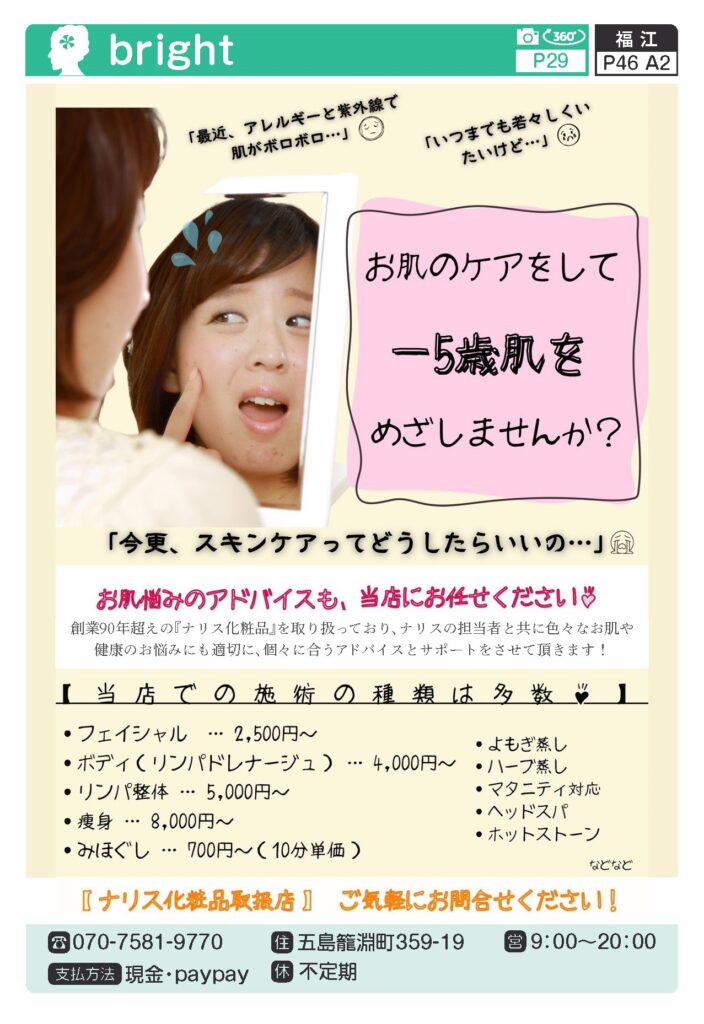看板猫がお迎えする、自己免疫力をあげる温活にフォーカスしたサロン
檜の香りのする酵素風呂や自分に合ったハーブを使ったハーブテントで体を温めながらリラックスした空間をお過ごし下さい。
メニュー
◆ 酵素風呂 3,500円~
◆ ハーブテント 2,500円~
初回島民割ございます
※予約優先
店舗情報
| TEL | 090-7094-9249 |
|---|---|
| 住所 | 五島市松山町216 |
| 支払方法 | 現金・カード・他 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 休み | 不定休 |
プライベートで隠れ家的な「女性専用」リラクゼーションサロンがOPEN
日々のお仕事や家事で「肩が腰がしんどい」「ストレスでなんだかダルイ…癒されたい」「眠りが浅くて疲れがとれない」などなど。オイルマッサージで気持ちよくスッキリさせませんか?
メニュー
◆ 全身オイルマッサージ 75分 6,500円 95分8500円
(足湯&着替え15分)SETメニュー ヘッドスパ・足裏ソフレ
| クーポン | 島民初回割 2,000円OFF(島民以外のお客様は1,000円OFF)(クーポンの利用はこちら) |
|---|
店舗情報
| TEL | 070-8304-3630 |
|---|---|
| 住所 | 五島市増田町345-2 |
| 支払方法 | 現金 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 休み | 不定休 |
| 駐車場 | あり |
澄んだみじょか心と錆びないカラダ作り

『みじょカラ』始まります!心身デトックスストレッチ『リラックス』やるごとに柔軟性upストレッチとコアトレの『スキルアップ』ダンス基礎を入れた楽しい『リズム』それぞれ30分好きな物を選び楽しんで下さい。
詳細はInstagram、LINEで!
メニュー
① 「みじょカラ リラックス」500円(30分)
② 「みじょカラ スキルアップ」1,000円(30分)
③ 「MIJO KARA リズム」1,500円(30分)
店舗情報
| 営業時間 | 平日 9:30~11:30 / 19:00~21:00 (予定)
土日(どちらか)9:30~11:30 / 14:00~16:00 (予定) |
|---|
fullyGOTO2022秋号 表紙の顔 高橋 和希さん

今回表紙を飾ってくれたのは、高橋 和希(たかはし かずき)さん 29歳。千葉県から五島列島福江島に移住して 2年目。10年以上のキャリアを持つ美容師である彼は、その技術や経験を活かし、現在は訪問美容師として働いています。依頼があればどこへでも。フットワークの軽さや人当たりの良さも手伝って、リピーターも増加中。そんな高橋さんに、移住した経緯や現在の暮らしについてお聞きしました。
導かれるように五島へ
高橋さんは、茨城県出身。高校卒業までご実家のある茨城で暮らした後、18歳から28歳までの約10年間、千葉県で美容師をされていました。「5年間ぐらいは勤めでやってましたけど、後半はフリーランスでした。」ほぼ同じ繰り返しの毎日の中で、ふと、どこかへ旅行に行きたいなぁと思い始めます。そんな時、ぼんやり観ていたテレビ画面に映し出された福江島の景色に目が留まります。「多分高浜だったと思いますが、すごく奇麗で、ここに行ってみようと直感で決めました。」福江島に移住することとなる2年前の出来事です。
きっかけは偶然の出会い
初めて訪れた五島福江島。それも人生初のひとり旅。「特に計画も目的もなく、テレビで見た景色の中に身を置いていることに充実感を抱きながら数日を過ごしていました。移住することになるなんて全く考えず。」そんなある日ふらっと入ったカフェでの出会いが、彼の人生を一変することとなるのです。「店のオーナーが気さくな方で、どこからきたの?と話しかけられ会話をしていたら、たまたまその店に居合わせた方が五島市役所の移住担当の方だったんです。流れで移住の話になり、聞いているうちに次第に引き込まれていきました。」高橋さんの中で、何かが動き始めた瞬間でした。千葉に戻ってからも、担当の方とオンラインで何度か面談をし、移住へと気持ちが傾き始めたころ、地元福江島で起業した、同年代の男性を紹介されます。その方は、ご自身も美容師でありながら、美容のトータルプロデュース事業を展開する計画をしていて、その中のひとつである「訪問美容」をやってみないかと誘われます。「正直、美容師はもういいかなぁと思っていたんですが、せっかく美容師であることが導いてくれたご縁なので、引き受けることにしました。」
流れに身を任せて
そのあとは話がとんとん拍子に進み、初めての旅行から1年後の移住に向け準備を始めます。そんな矢先のコロナ禍到来。計画より年1ずれ込みましたが、令和3年8月、晴れて五島市民となりました。初めは移住希望者用の短期滞在住宅に3ヶ月住み、その後タイミングよく空き家バンクで気に入った賃貸物件が見つかり引っ越します。「最初一人暮らしには広すぎるかなと感じていましたが、この4月には千葉から彼女も移住してきたので、二人と犬一匹と、快適な暮らしをさせていただいています。」五島市の人口増加にも貢献してくれている高橋さんです。
訪問美容師として
現在は、主に訪問美容師として、老人ホームなどの施設や、個人宅に出向き、ご希望に合わせたシャンプーやカットを行っています。客層は高齢者や障害のある方、また小さなお子さんや、そのお母さんなど幅広く、訪問先も、福江市街地から遠くは玉之浦まで行くこともあるそう。「それまで訪問美容の経験がなかったので、最初は専用の機械や道具の扱いに苦戦したり、寝たきりの方への対応に戸惑ったりすることもありました。また福江の中心部だと、道が入り組んでいて訪問先までたどり着くのに時間がかかったり、駐車スペースがなかったりと、ちょっとだけ大変なこともあります。ですが、終わった後にお客様から喜んでもらえると、全てが帳消しになりますね。今後も、美容室に出向くのが困難な方の、文字通りかゆいところに手が届くサービスを心掛けていきたいと思っています。」
趣味を満喫できる福江島
趣味は釣りとキャンプ。どちらも思い立ってすぐ実行できるのが島暮らしの醍醐味。「釣りは主に防波堤や岩場などの陸から、ルアー釣りが多いです。イカやカマスなど、その時期に釣れるものを狙っています。キャンプは基本ソロで、釣った魚を焼いたり刺身にしたり。自然の中に身を委ね、ひとり気ままな時間を過ごせるところが気に入っています。」人生とは偶然の積み重ね。予定通りに行かないからこそ、時には流れに任せてみると、色んな偶然が自分が一番心地よい場所へと導いてくれるのかも知れない。誰一人知り合いのいなかったこの土地に、導かれるように移住してきた高橋さんから、そんなことを教えてもらったような気がしました。
【訪問美容サロン サークル】電話:050-5896-2533
【取材・執筆・掲載】fully編集部
【掲載先】fullyGOTO2022秋号
 浜方ふれあい館 館長 福井 ルリ子さん
浜方ふれあい館 館長 福井 ルリ子さん
宇久島の港から海沿いを歩くこと15 分、旧宮崎缶詰所と書かれた建物が。ここは現在、体験型施設として「浜方ふれあい館 (はまがたふれあいかん)」に生まれ変わり、福井ルリ子さんが館長を務めています。

福岡から宇久島へ
ルリ子さんは福岡出身。ご両親が宇久島出身ということもあり、子供の頃から宇久島を訪れる機会がありました。そして、そろばん教室で講師をしていたルリ子さんは、教え子たちを連れて宇久島を訪れます。
「大人になって来てみた時、なんて綺麗な場所なんだろうと思っていたら、縁あって結婚を期に宇久島に住むようになって。今でも、下り坂から見える港と海の景色に癒されています。」ルリ子さんは今も、平日の月曜日と水曜日はそろばん教室を行い、土日祝日にふれあい館を運営しています。

自分たちの力で
「宇久島に来て一番驚いたのは、コミュニティーの繋がりの強さと、みんな何でも自分達でやるという姿勢。最初はついて行くのに必死でした。このふれあい館も、地域の人たちの力で作られたものなんです。」缶詰工場が閉鎖し、建物だけの状態となって漁師さんに売却された本館を、平成20年に地元の人たちで協力し改装。文化継承を行う場所を作るため、地域の皆さんの想いが詰まった場所となりました。


いろんな人が集える場所
ふれあい館では、鯨の骨や、供養塔の写真、漁をしていた頃の写真、巨大な鮑の殻などを展示しています。「訪れた方が、もし観光の方と分かれば、説明をさせていただいています。主人は生まれ育ちが宇久島で、とても詳しいのですが、まだまだ私は勉強中なので、地元の人からいろいろ教わっています。」そして、海士(あまんし)や捕鯨の歴史文化を知ることができる場所であると共に、憩いの場としてもひらかれているふれあい館「。子供の遊び場が無いので、駄菓子やくじ引きを置いています。遊びがてら集う場になって、宇久の歴史も自然と知ってくれたら良いなと思って。」カフェスペースもあり、メニューはソフトクリームとドリンク類、夏にはかき氷が加わります。

鮑、サザエ、そして鯨
宇久島は、鮑とサザエがよく取れる地で、全盛期には解禁日に人100kgを揚げてくる漁師さんがいたほど。温暖化等が原因か、近年では数が激減してしまいましたが、アワビがわずかで、サザエが若干水揚げされています。そして近隣の島々と同じく江戸時代ごろから捕鯨が始まり、これも大切な産業の一つでした。南氷洋捕鯨(南極の海)へ行く人たちもおり、帰ってきた際はお土産としてたくさんの鯨が皆に配られました。なので、鯨肉は一番身近で豊富なもの。そんな歴史から、鯨商品はここ浜方では今でも定番の品です。ふれあい館では現在も地元の人がよく買いに訪れます。
「島ではレンタカーや電動自転車の貸出があり、どこかに行く前に寄っていかれる方も多いです。平日も、事前に電話をいただいて予定が入っていなければ開けることも可能です。自動販売機もあまり無い土地なので、海に行く時の飲み物だったり、お土産品だったり、利用して頂ければと思います。」
コロナ禍で減った観光客も、少しずつ回復している様子。「今の夢は数年中止となっている七夕まつりを復活させること。やはりお祭りは皆が集まって楽しめるイベントなので、ないととても寂しいので。大人は三線のコンサートを聴き、子供等はゲームや駄菓子で楽しむ、そんな時間をまた作りたいです。」子供から大人、地元の人から観光客まで、様々な人たちがいろんな形で利用する浜方ふれあい館。ルリ子さんが目指す「気軽に交流できる場」として、これからも地域の皆さんと一緒に歴史を繋ぎます。宇久島へ訪れる際は、ぜひお立ち寄りください。
基本情報
浜方ふれあい館
電話:0959-57-2378
住所:〒 857-4901
長崎県佐世保市宇久町 平 3281-79
営業時間 :9:00 ~ 16:00営業日 :毎週土・日曜日・祝祭
(事前予約にて平日でも対応可能です。)
休日:平日
料金:無料
アクセス:< フェリー > 佐世保港から約 200 分、直行便で約 145 分、平港着後、徒歩約13分。
インスタグラム (DMもOK)
【取材・執筆・掲載】fully編集部
【掲載先】fullyGOTO2022秋号
地元漁師と船上での魚釣り体験

かつて捕鯨や鰹節業が栄え、サンゴ加工の名地でもある富江。この富江で釣り体験ができるという事で行ってきました。8時30分、黒瀬漁港の奥の特に目立つ、水色の桟橋が集合場所の目印です。近くには駐車できる空き地があるので、車数台で来ても安心です。今回、釣りを教えてくれたのは、元保安船で働いていた滝川洋一さん。道具は全て滝川さんが準備してくださっており、こちらで用意するものは一切なし。気軽に参加できるのも釣り体験のメリットではないでしょうか。 長靴を履いて、ライフジャケットを着たら、「DORAGON」」に乗船。20分間波に揺られて釣りスポットへと向かいます。

取材日は大瀬埼灯台の近くで釣りをしましたが、潮の満ち引きや滝川さんの判断によって、様々な所で楽しめます。釣り場に着いたら撒き餌の投げ方や糸の引き方などを徹底的にレクチャーされました。

釣り竿を触ったことすらない初心者でしたが、開始3分でヒット!この日初めての魚を釣り上げることができ、どよめきが起こりました。狙いはアカハタでしたが、この日は高級魚である1・2㎏のアコウの釣り上げに成功。滝川さんも「俺も久しぶりに見た」とはにかんだ笑顔を浮かべていました。

釣り開始から2時間でアコウ1匹・ベラ2匹・クチビ3匹・アカハタ8匹の計14匹を釣り上げ、参加者もガイドの滝川さんも大満足の結果となりました。

最初は船の揺れで立つのもままなりませんでしたが、帰り際には船の上が名残惜しくなるほど貴重で有意義な時間でした。船に乗り、五島の潮風を浴びながら釣りの聖地での釣り体験。陸からとはまた違う五島の景色が見られるのも魅力です。小学生のお子様づれにもオススメですよ。
【主催・お申し込み先】五島市体験交流協議会 株式会社JSH
【電話】0959-76-3600
【受付時間】9:00~18:00(土日祝を除く)
体験についての詳細はこちら
【取材・執筆・掲載】fully編集部
【掲載先】fullyGOTO2022秋号
民泊を営むご夫婦と魚釣り体験

奈良尾港から車で20分ほどの所にある静かな港町「宿ノ浦」。
小さな港に連なる「やだい」と呼ばれる小屋の形をした筏は、アコヤ貝の養殖が盛んだった頃の名残だそうで、この集落を象徴する風情ある景色です。
ここで、釣り体験をさせてくれると聞き、「かずおばんの家」という屋号で民泊を営むご夫婦を訪ねました。明るくて優しいお母さんと、漁師堅気で真っ黒に日焼けしたお父さんが迎えてくれます。

すぐそばにある体験場所まで案内してもらい、陸と繋がる筏に固定してある小船に、ひょいと乗り込みます。ほぼ陸なので安全ですが、人の動きに合わせ微妙に揺れるので、さながら船釣り気分。

竿やリールの扱い方なども最初から丁寧に指導してくれます。餌を海中に拡散させて魚の群れを寄せ集めるサビキ釣りを行いました。サビキ釣りは、「サビキ」と呼ばれる擬似針で釣り上げるので、針に餌を付けたり、仕掛けを遠くに投げる必要がありません。餌カゴを水中へ沈めて、上下させると、サビキが踊って魚たちを集めます。

餌カゴに入れた餌も撒かれることになるので、集魚効果はバッチリ。魚が食いついた時の引っ張られる瞬間や、複数付いているサビキに、2匹、3匹と連なって釣り上がった瞬間は気分も上がり、なかなか止められなくなるかも。海水が澄んでいて、魚の群れや餌が海に広がる様子が鮮明に見えることも、楽しさを倍増させます。

またインストラクターである「かずおばん」のネイティブな五島弁が聞けるのも、この体験の隠れた魅力。体験料金には竿やリール、餌代も含まれているので、手ぶらでOK。釣った魚は、希望すれば持ち帰りも可能です。また、釣れるのはアジやサバなどの幼魚なので、触る体験もハードルが低く、初心者や小さいお子さんも楽しめます!
【主催・お申し込み先】新上五島町観光物産協会
【電話】0959-42-0964
【受付時間】8:30~17:00
体験についての詳細はこちら
【取材・執筆・掲載】fully編集部
【掲載先】fullyGOTO2022秋号